アジア現代美術 『ブーム』の表と裏
黒田雷児
R202216
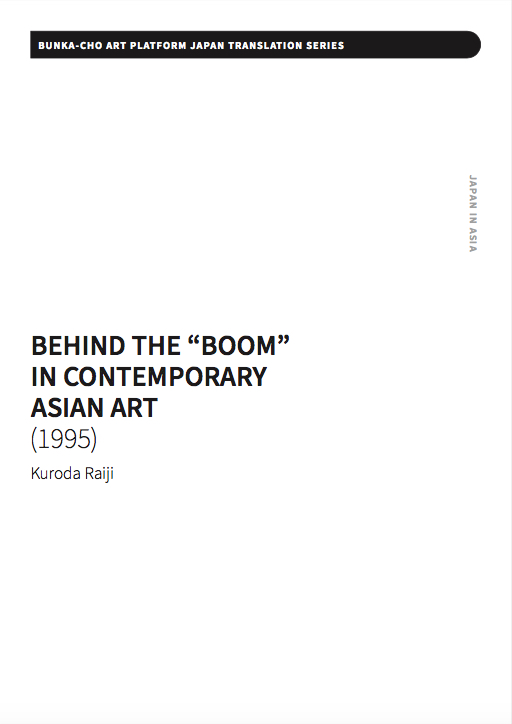
「アジア現代美術」というメイン・タイトルと「「ブーム」の表と裏」というサブ・タイトルをもつ本論考は、当時、福岡市美術館に学芸員として勤めていた黒田雷児によって執筆され、1995年・春号の『季刊アートエクスプレス』に掲載された。
本論考で、黒田は「アジア現代美術ブーム」について論じ、日本でアジア美術への関心が高まってきた社会的・経済的背景を分析している。この言葉は、日本各地でアジアの現代美術展が開催されていた当時の状況を指して、マス・メディアが用いたものであるという。日本におけるアジア美術への関心の高まりを喜ばしい傾向であるとしながらも、1979年の開館以来、長らくアジアの近現代美術を日本に紹介することを主要なミッションとして活動してきた福岡市美術館の学芸員として、黒田は、この言葉にある種の「軽薄さ」と「東京中心主義」を看取する。
黒田が、後小路雅弘ら先駆者たちの批判的視座を受け継ぎながら、「アジアは多様だ」など、欧米中心的・日本中心的な視点から構成された、アジア美術を語るときのクリシェや固定化された見方に対して警鐘を鳴らしていることは重要である。そうしたクリシェや固定化された見方は、現在でも、日本におけるアジア美術に関する言説のなかで頻繁に見られる。それに対し、黒田は、本論考の終盤で、こうした「ブーム」のなかで等閑視されがちな滞在制作の重要性を指摘し、そこから抜け落ちる「フォークアート」や「韓国民衆美術」などの動きに目を向けている。
黒田は、その後、1999年に開館した福岡アジア美術館に学芸員として勤め、各地のアジア美術を日本に紹介する多くの展覧会を企画する一方、2014年にアジア美術に関して自身が書いたエッセイを集めた『終わりなき近代 アジア美術を歩く2009–2014』(グラムブックス)を刊行した。
- 題
- アジア現代美術 『ブーム』の表と裏
- 著者
- 黒田雷児
- 初出
- 1995
- 翻訳
- ロー・シーリン
- 編集
- 黒田雷児、マイク・フー
- デザイン
- イエン・ライナム
- テーマ
- アジアの中の日本
- サイト公開
- 2023-03-02
- 更新日
- 2023-03-02
© 2022 Kuroda Raiji + Bunka-cho Art Platform Japan
当ウェブサイト (https://artplatform.go.jp) で公開している英訳文献は、教育・研究・批評・調査などの目的に限り、許諾の申請をすることなくご利用していただくことができます。ただし、英訳文献を有料で販売又は配信することを目的とした複製による利用はできません。利用の際は、英訳文献の利用規約に従ってください。
- サイテーション
- Footnote/endnote: Kuroda Raiji, "Behind the 'Boom' in Contemporary Asian Art," trans. Shi-Lin Loh, Bunka-cho Art Platform Japan, posted March 2, 2023, artplatform.go.jp/readings/R202216.
Bibliography: Kuroda Raiji. "Behind the 'Boom' in Contemporary Asian Art." Translated by Shi-Lin Loh. Bunka-cho Art Platform Japan. Posted March 2, 2023. artplatform.go.jp/readings/R202216. - 原書情報
- 黒田雷児「アジア現代美術 『ブーム』の表と裏」『季刊アートエクスプレス』6号(1995年春)、32–42頁。
Kuroda Raiji “Ajia gendai bijutsu: ’Būmu’ no omote to ura” in Art Express, no. 6 (Spring 1995): 32–42. - 国立国会図書館(NDL)リンク
- ISBN
