日本軍政と東南アジアの美術
後小路雅弘
R202116
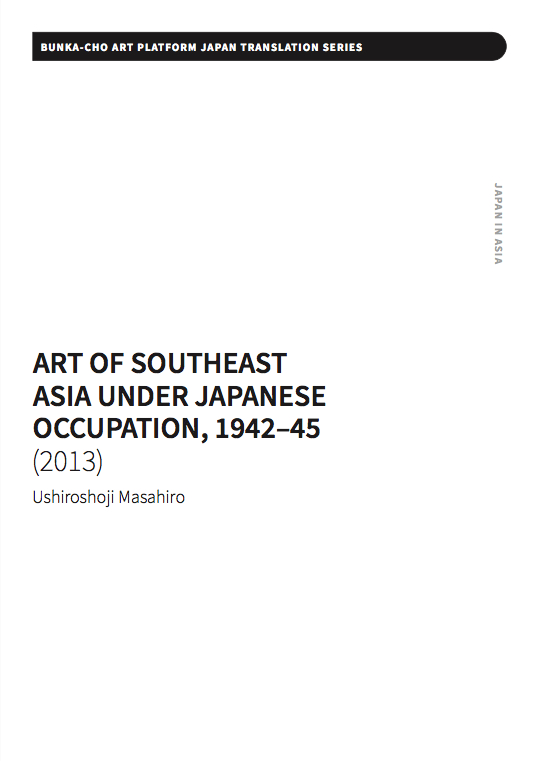
本論考は、福岡市美術館・福岡アジア美術館で学芸員を務めた後小路雅弘(1954–)が、第二次世界大戦中の日本軍政による東南アジア地域占領が、同地域の美術史に与えた影響と意義を論じたものである。
後小路は未調査のミャンマーを除く、東南アジア各地の日本軍政下の状況を振り返り、日本軍の占領以前の美術動向は散発的で、地域によって異なり、その上、占領下での宣撫工作の方針も一貫したものではなかったと指摘する。後小路は、宣撫工作に関わった日本人が、朝鮮や台湾に求めていた「ローカルカラー/地方色」「アジアらしさ」を、東南アジア各地にも同じように要求していたことを明らかにした上で、そうした類型から逸脱しようとする美術家たちの意志を、わずかに現存する作品から読み取るためには、個々の作品研究を積み重ねるしかないと論じている。
日本における東南アジアの現代美術の紹介は、後小路が在籍していた二つの美術館と国際交流基金が重要な役割を果たした。福岡市美術館は1980年の「アジア現代美術展」以来、積極的にアジアの現代美術を紹介する役割を果たし、これを母体として1999年に福岡アジア美術館が開館した。同館はアジア近現代美術の収集と展示を行う一方で、「福岡アジア美術トリエンナーレ」を開催し、アジア現代美術の調査や美術家との交流を推進したが、2014年の第5回を最後に開催されていない。
国際交流基金の活動については、本事業で英訳した古市保子「アジアの新たな関係性の構築に向けて 国際交流基金アジアセンターの活動」(『美術フォーラム21』11号、2005年2月)を参照されたい。
- 題
- 日本軍政と東南アジアの美術
- 著者
- 後小路雅弘
- 初出
- 2013
- 翻訳
- ロー・シーリン
- 編集
- 後小路雅弘、ヨンシャン・ガオ
- デザイン
- イエン・ライナム
- テーマ
- アジアの中の日本
- サイト公開
- 2022-06-15
- 更新日
- 2022-06-15
© 2021 Ushiroshoji Masahiro + Bunka-cho Art Platform Japan
当ウェブサイト (https://artplatform.go.jp) で公開している英訳文献は、教育・研究・批評・調査などの目的に限り、許諾の申請をすることなくご利用していただくことができます。ただし、英訳文献を有料で販売又は配信することを目的とした複製による利用はできません。利用の際は、英訳文献の利用規約に従ってください。
- サイテーション
- Footnote/endnote: Ushiroshoji Masahiro, "Art of Southeast Asia Under Japanese Occupation, 1942–45," trans. Shi-Lin Loh, Bunka-cho Art Platform Japan, posted June 15, 2022, artplatform.go.jp/readings/R202116.
Bibliography: Ushiroshoji Masahiro. "Art of Southeast Asia Under Japanese Occupation, 1942–45." Translated by Shi-Lin Loh. Bunka-cho Art Platform Japan. Posted June 15, 2022, artplatform.go.jp/readings/R202116. - 原書情報
- 後小路雅弘「日本軍政と東南アジアの美術」、『哲学年報』72輯(2013年3月)、49–72頁。
Ushiroshoji Masahiro, “Nihon gunsel to Tōnan Ajia,” Tetsugaku nenpō, 72 (March 2013), 49–72. - 国立国会図書館(NDL)リンク
- https://id.ndl.go.jp/bib/024608889
- ISBN
